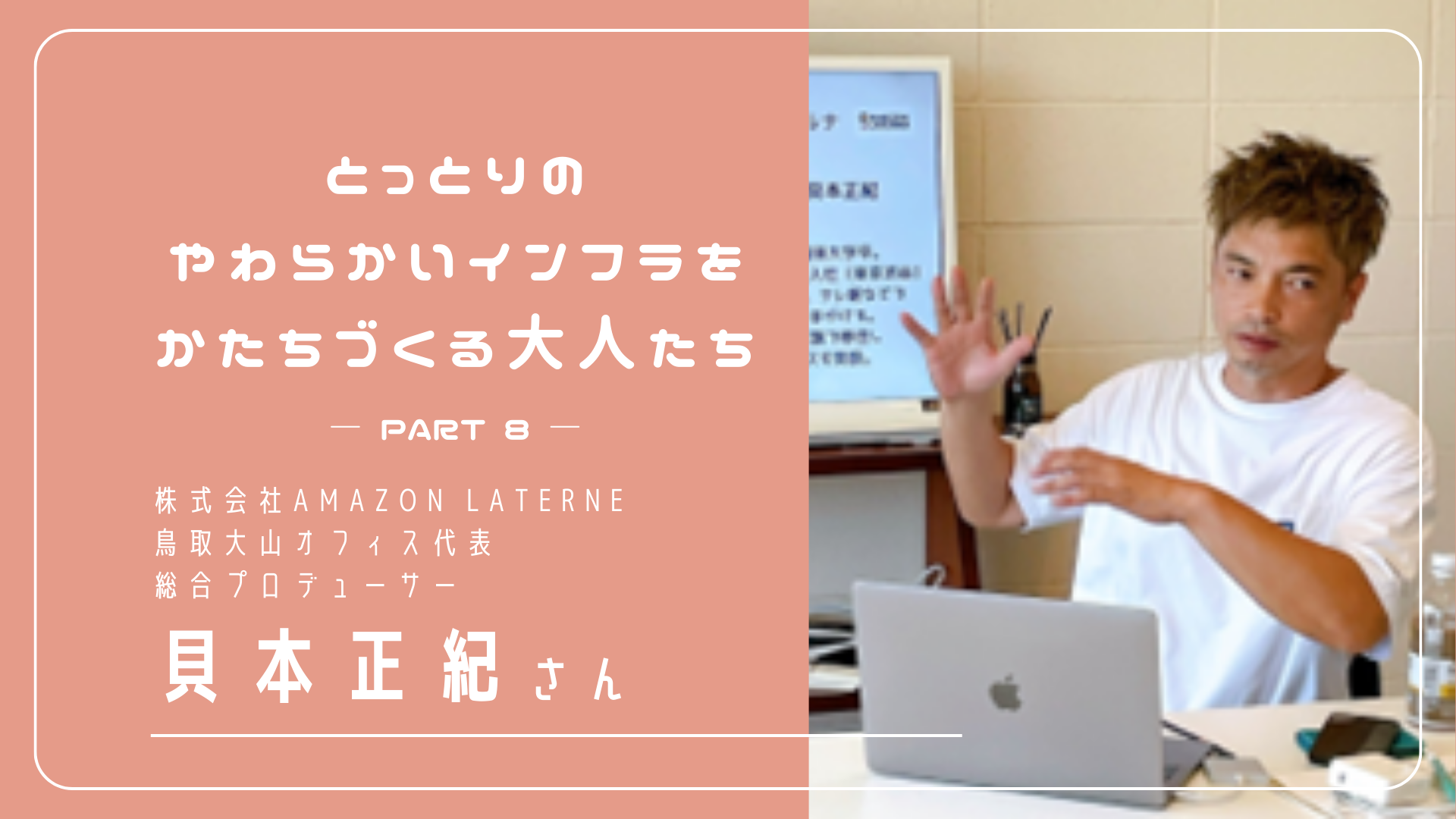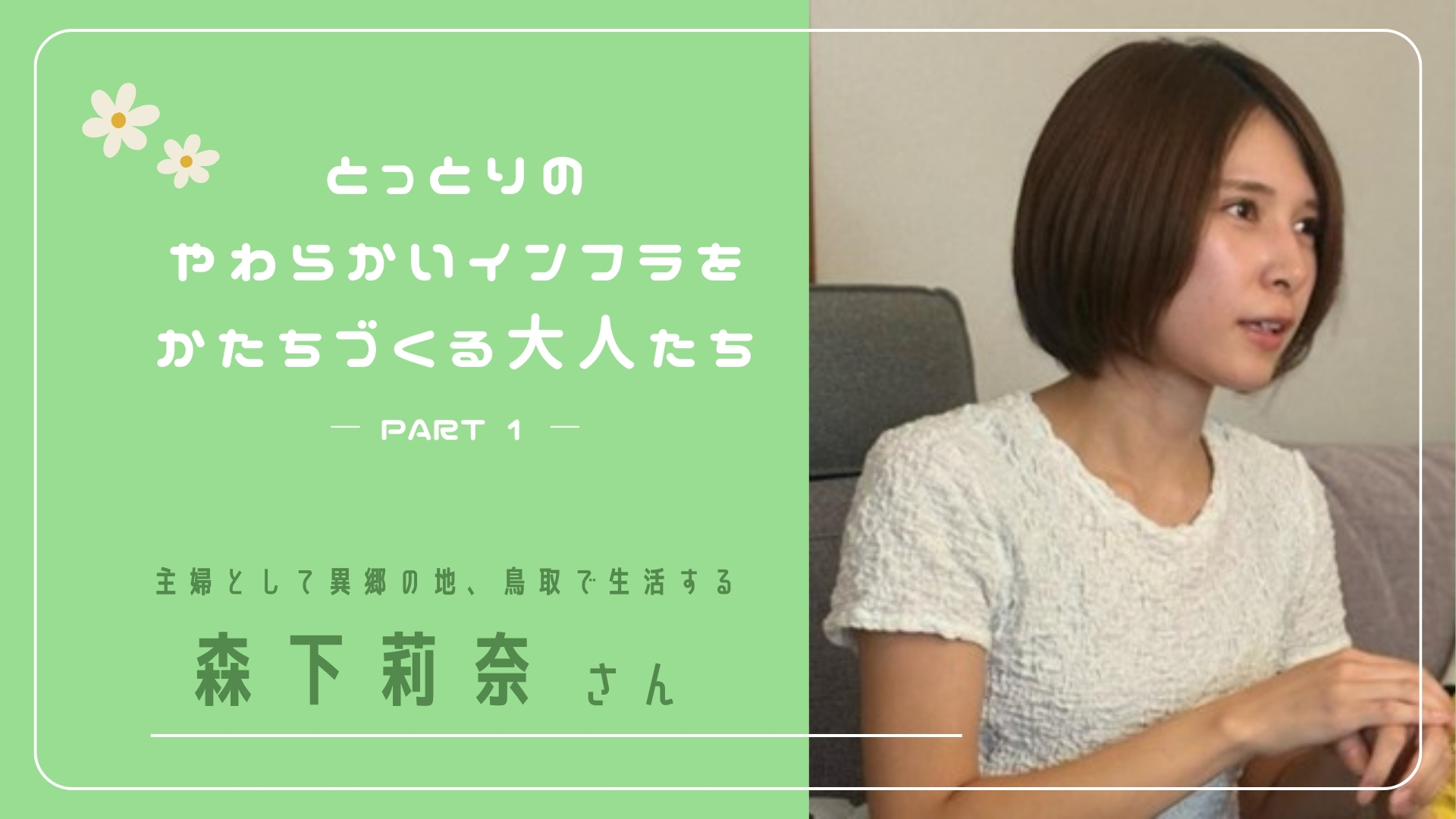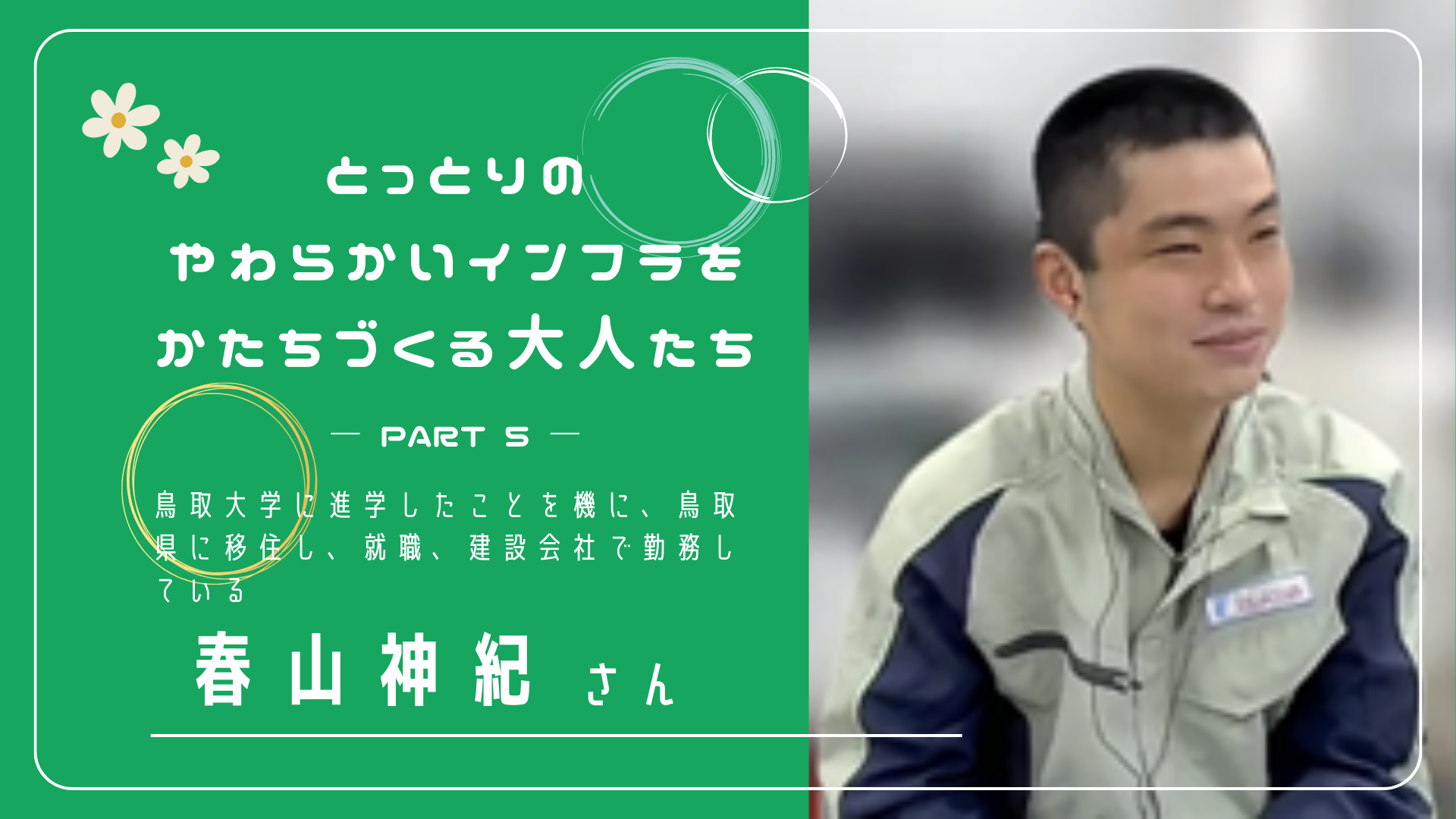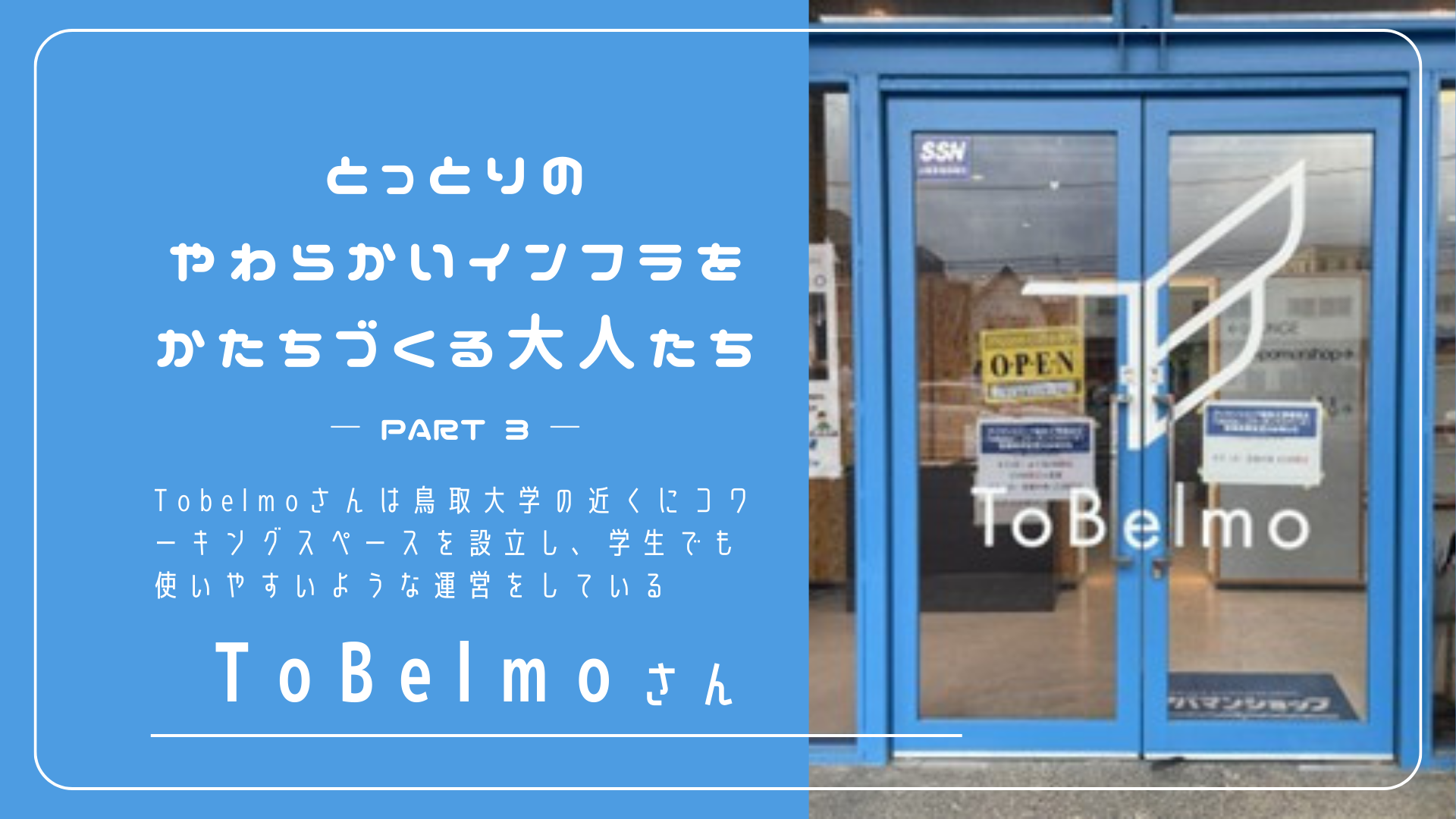<TORICOとは?>
2020年7月、レストラン「BIKAI」の2階の使われていなかったイベントスペースを活用してスタート。TORICOは、県外、東京と、鳥取の大山の人を繋ぐためのスペースとして生まれた。11事業社(フリースクール、学習塾、デザイナー、アウトドア会社など)が籍を置いている。
名前の由来は、この町の虜”TORICO”にする、とっとり(TOTTORI)のコワーキングスペース(Coworking space) という意味。
*TORICOの推しポイント*
①ワークスペースがオーシャンビュー
独り占めできる海が見える解放感がある
作業も捗る!!

②チャレンジャー募集!
新しい挑戦をしたい人が集まれる場所
新たな熱意、大歓迎!

③地域の外と中を繋ぐ場所
大山町内の人を中心に、地域の方々を繋いで、新規事業を生み出す、仲介役のような機能をもっている!
*
【TORICOのキーパーソンにクエスチョン!】
テレビプロデューサー 貝本正紀さん
<プロフィール>
奈良県橿原市出身
早稲田大学へ進学後、東京にあるテレビ番組制作会社アマゾンラテルナ入社。
現在は同番組制作会社 アマゾンラテルナの鳥取大山オフィスを立ち上げ、大山チャンネルやTORICOを運営中。
Q.鳥取に移住されたきっかけを教えてください
地方から新しいテレビの形を模索したかった。そのチャンスを与えてくれたのが、たまたま鳥取県大山町だった。
NHKの取材で鳥取を訪れた際、地域活動に関心があることを話すと、現地の関係者から「鳥取で起業してみてはどうか」と提案を受けた。そこから町の職員が担っていた「大山チャンネル」を民間に委託する話が進み、それを機に移住を決意した。
Q.普段どんな生活を送っていますか?
拠点が鳥取の家、大山の家、大山オフィスと複数あることで、自然と人との出会いが増えていく。拠点が2つあれば、出会いも2倍になる。移動するからこそ生まれるつながりがあり、それが仕事にも良い影響を与えている。
休日は家族との時間を大切にし、仕事のことは考えないようにしている。ショッピングモールに行くなど、ごく普通の時間を過ごすことが、仕事に集中するための土台となっている。家族との関係がうまくいかなければ、仕事もうまくいかない。だからこそ、仕事と同じくらい家族との時間を意識的に確保し、関係を育んでいる。
また、面白いことや新しいアイデアを考え、それを誰かに伝えてリアクションをもらうのも趣味の1つかな。それがそのまま仕事にもつながっている。
Q.どんなお仕事をされていますか?
株式会社AMAZONLATERNA (アマゾンラテルナ)の鳥取大山オフィス代表として、「大山チャンネル」の総合プロデューサーを務めている。番組全体の総合演出を担い、長期的な視点を持ちながら企画を組み立てている。
主な業務は、テレビ番組制作のための企画立案や準備、予算の管理など。

Q.アマゾンラテルナ(TORICO運用元)が制作している、大山チャンネルについてもう少し教えてください
「地域の人による、地域の人のためのチャンネル」というコンセプトのもと、大山チャンネルを制作している。出演するのは、意識の高い町民だけではなく、小学生、ブロッコリー農家、水道課の課長補佐など、沢山の人がテレビに関わっていて、町全体を巻き込みながら番組を作っている。現在、大山町の人口15,000人のうち、5100人が番組に出演している。
大山チャンネルの特徴として、「テレビで見たことのない人」にこそ出演してもらっている。絵が得意な人にはセットを描いてもらい、スマホを使って動画を作ってもらってそれがテレビで使われたりと、自分ができる形でテレビに参加してもらう。
出演することで友人から一目置かれたり、新たな人とのつながりが生まれたり、キャリアの選択肢が広がることもある。また、子どもや孫が出ることで興味を持ってもらえる。地元の飲食店では子どもたちが食レポをして、正直な感想を伝える。少年野球のチームが部員不足や資金難に悩んでいるといった地域の課題も、大山チャンネルを通じて、助けを求める人と支援できる人が自然とつながる場が生まれている。
大山チャンネルは、地域の人々同士をつなぐ"仲介者"のような存在。ただ番組を面白くするだけでなく、出演した人同士が仲良くなれるかどうか、新たな繋がりが生まれるかどうかを逆算しながら企画を組み立てている。
予算もない、お金のない、人もいない。しかし、地域のつながりを最大限に生かした番組づくりを続けた結果、大山チャンネルの満足度は85%に達している。他社の番組と比べても、その満足度の高さは際立っている。
Q.TORICO運営の思い、今後の展望を教えてください
今までのインフラは、社会を成長・発展させるもので、これからはそれを成熟させる時代になると思う。今現在の状況をより充実させるか、豊かさの価値観を変えていく必要があるのではないかなと。都会と同じような豊かさを追い求めていたら、いつになっても田舎は豊かになれないと思っているので。
だから、これからの時代のインフラは今までの道路とかのハード面のインフラじゃなくて、自然や人が集う場とかのソフト面、豊かな体験ができる基盤としてのインフラが重要になってくると思う。
やわらかいインフラの要素(カフェやパン屋さん)が色んな場所にポツポツと点在するだけじゃなく、広い面になって存在していくといいよね。そうしたら、各所に訪れた人が、例えば地域に参加する人になって、企画する人になって、地域の人を繋いで関係人口が増えて、地域が活性化されていい傾向につながる。
TORICOはやわらかいインフラの中でいうコワーキングスペースに当たると考えると、テレビの中でだけでなく、テレビの外で集まれる場所として、新しいことや事業を始めたり、さらに密度の濃い繋がりや関係性を築ける場所にしたいね。いかに身近な人を幸せにしていくかを大切に、地元の人と密な関係を築きたい人がやって来れるようにしていけたら。
具体的には、新しい企画、起業に挑戦したい人の相談にのって、TORICOの訪問者とともに考えをまとめていくのを支えていきたい。挑戦する上で一番大変な、初めの第一歩のハードルを下げて、乗り越えるのを支援していく場として引き続き運営していきたい。
初めの第一歩のハードルを下げてくれる場を見つけるのはなかなか難しい。
だから、誰もが挑戦しやすくなるTORICOは貴重な存在だ。
Q.若い人へメッセージや、思いがあれば教えてください
例えば大学で学んできたことややってきたこと、専門の知識、技術を生かして地域と繋がったり、関わってほしい。大山町には課題が沢山あり、そういった物件や人脈は紹介できる。地域に搾取される形じゃなくて、お互いWin-Winな関係をつくれたら面白いのではないか。
今まで学んだことや趣味で得た知見を地域側に伝えることで、地域にとってプラスになることもある。地域の人にはない、新たな考えを取り入れることで、地域が良くなっていくこともあるので、積極的に地域とつながってみてほしい。
Q鳥取の好きなところ、いいところを教えてください
鳥取の一番の魅力は、圧倒的に人が少ないこと。これこそが鳥取の強みだと思っている。
例えば、お店も海も独り占めできる。都会では遊びに行くにも人混みでストレスを感じることが多いが、鳥取ではそんな心配はない。その分、人とつながりやすい環境があり、「知り合いの知り合いは、知り合い」という感覚が自然と生まれる。
さらに、手軽に触れられる自然がたくさんあるのも魅力のひとつ。海や山といった自然がすぐそばにあり、気軽に楽しめる。
そして、鳥取産の新鮮な野菜の美味しさも格別。収穫したての野菜は、ブランド野菜よりも鮮度が高く、シンプルにその美味しさが際立つ。


「人がいないって1番の贅沢だよね」インタビューメンバーも改めて認識。
お忙しいところ、ありがとうございました!
…✩…✩…✩…✩…✩…✩…✩…✩…✩……✩…✩…✩…✩…✩…✩…✩…✩…✩…
<貝本さんに教えてもらったおすすめのとっとりのやわらかいインフラを体験してみた!>
美味しいコーヒー(カフェ)
・カフェ2020(つれづれ)
JR大山口駅前という好立地にあるおしゃれなカフェ。名物の「ドゲナサンドプレート」は地場の新鮮な野菜やお肉がふんだんに使われたメニュー。オニオンスープがやさしく印象に残り、もう一度行きたいお店。お店の2階からは、海や風車、時たま、汽車が通るのを見ることができる。海を感じながらゆっくりご飯が楽しめる、素敵なお店。


最高のパン
・ichi bakery
大山町妻木にある、空き家を使って始められたパン屋さん。地域の人たちに来てほしくて、地域の人のために、パンを作られているそうだ。田んぼに囲まれたのんびりとした雰囲気がある。
私は、クリームパン、チーズのパンを食べた。どちらも美味しく、久しぶりにパン屋さんのパンをいただいた。食べてみて、パン屋さんのパンは、いいなと改めて思った。


<貝本さん!鳥取の豊かなインフラを体感してみた!>
・豊かな自然 〜豊成海岸〜
水平線が見える 美しい海。
人が居ないので独り占めできる。何という贅沢だろう。
鳥取砂丘とはまた見え方の違う日本海を感じることができた。


・豊かな食 〜鳥取産、ありのままの採り立て野菜〜
貝本さんのインタビューにもあったように、鳥取産の新鮮な野菜の美味しさは格別。収穫したての野菜は、鮮度が高く、シンプルにその美味しさが際立つし、それをご近所さんからのお裾分けや直売所でいただける。俯瞰してみると都会では体験できない、なんて贅沢なことなんだろう。


★取材した感想★

「智頭で 「はい。ち〜ず!」がどうしてもしたかった愉快な愛され澪ちゃん(笑)」
鳥取の人口減少の問題を増やす方に考えるのではなく、「人が少なくてもいいんじゃないか、人が少ないから、絶景を独り占めできるという贅沢が味わえるのではないか」という貝本さんの意見を聞き、鳥取の人口減少に対して、新しい視点からの考え方を知ることができた。
テレビを通じて地域と地域の人を繋ぐという発想に至ること、それを現実にしたことが私には無い発想でとても新鮮だった。
大学で学んだこと、研究していること、学生がもっている専門知識、技術、趣味などを地域側にも伝えてほしいこと、それを生かしていけたらいいのではないか。といったあたり
で、私にも地域の方々のためにも、できること、地域から学ぶこともあるんだと感じた。
学びは、覚えたり、理解したりするところで終わらずに、生かすところまでが重要ななんだと気づいた。そのことを忘れないように、これから、大学で学ぶことを地域の人達に伝えていき、私ができる形で地域に関われたらと思った。
もし、私が社会人になったら...
「こんな風に暮らしてみるのもアリかも」
ちょっと視点は逸れるが、私は、コウノトリに大変興味がある。貝本さんから、大山で繁殖していたコウノトリをテレビで追っていたこと、これからもコウノトリが住み続けられるためにはどうすればよいかという話を伺った。
私は高校生の頃に、家畜の堆肥で研究を行った。またコウノトリの郷公園のある、兵庫県豊岡市で行われている「コウノトリ育む農法」(環境保全型農業)に興味を持っている。そこから私は、堆肥や、田んぼの土壌についての学びから、「コウノトリ育む農法」をさらに改善できないかと、公立鳥取環境大学に進学した。
コウノトリを育める環境づくりのために、私の持っている知識、これから得る知識を活用して大学卒業後に、大山町のコウノトリを見守る方々と、試行錯誤しながら、コウノトリの生息する環境づくりに貢献することも良いかもかもしれないと思った。
<TORICO>
日本海が一望できるオーシャンビューのカウンター席、グループ向けボックス席、利用者と交流できる共有テーブル、オンライン会議も気にせずできるプライベートルームを完備。また、地域の内と外をつなぐゲートウェイとして、地元経営者との交流の場やローカルな暮らしを体験できる場をコーディネート。

 文字サイズ・背景色変更
文字サイズ・背景色変更